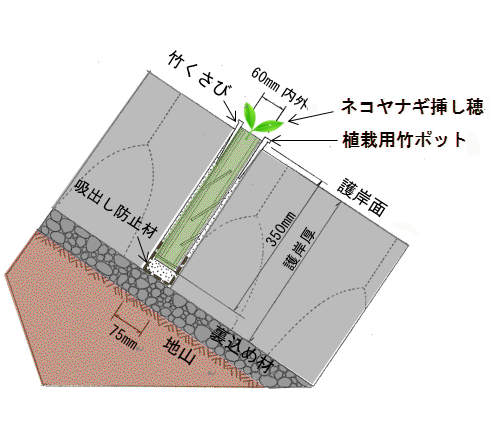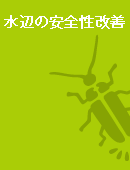生物多様性の原点 水際の環境改善
国民の生命・財産・暮らしを守るため、川は直線化され、堤防に挟まれ、コンクリート護岸で守られてきました。また、水の利用が増えて川の水量が減るなど、川の生き物は減り続け、2013年の環境省レッドデータブックによれば汽水淡水魚(対象400種)の内、約4割の魚種が絶滅危惧種となりました。さらに2014年にはニホンウナギがIUCN(国際自然保護連合)により絶滅危惧種に指定されました。
平成9年の河川法改正では「治水」「利水」と並んで「環境」を目的とする総合的な河川制度の整備を行うこととなり、一定の成果を上げてきましたが、これまで見過ごされてきた既設コンクリートの護岸には水際植生(エコトーン)の再生が望まれます。このような背景から短期間・低コストでできる「ネコヤナギ・エコ工法」は生まれました。
 無機質な水辺 |
 |
 「ネコヤナギ・エコ工法」による
水際植生(エコトーン)の再生
|
◆環境省公表「汽水・淡水魚類」(第4次レッドリスト)より
2013年に見直しが行われた環境省RDB(レッドデータブック)によると汽水・淡水魚(対象400種)の内、約4割の魚種が絶滅危惧種となり、準絶滅危惧種、地域個体群などを合わせると6割を超えている。淡水魚はますます減っている。
| カテゴリー |
1991年版 |
1999年版[2] |
2007年版 |
2013年版 |
備 考 |
絶滅危惧1類
(1A,1B合計) |
16 |
58 |
109 |
123 |
絶滅危惧1A類と絶滅危惧1B類の合計 |
| 絶滅危惧2類 |
6 |
18 |
35 |
44 |
|
| 準絶滅危惧、その他 |
24 |
29 |
82 |
82 |
|
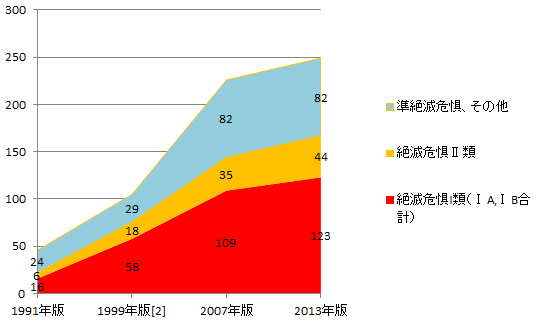
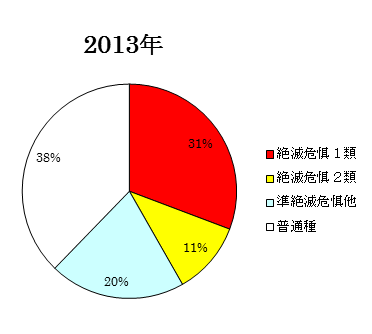
◆多自然川づくりポイントブックⅢより
COLUMN21 魚類等水生生物の環境改善では水際植物が重要
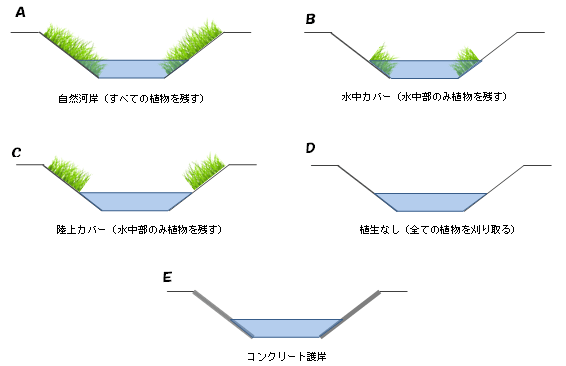
水際の構造と魚類などの生息量との関係では、A(自然河岸)>B(水中カバー)>C(陸上カバー)>D(植生なし)>E(コンクリート護岸)の順で生息量が少なくなった。
・・とされている。その点、ネコヤナギは陸上カバーと水中カバーを同時に満たし、最も生育量の少ないコンクリート護岸を自然河岸に近づけることができる特殊な植物と言える。
ネコヤナギってこんな木
ネコヤナギ(学名:Salix gracilistyla)は、ヤナギ科ヤナギ属の落葉低木。北海道から九州の山間部の渓流から町中の小川まで、広く川辺に自生しています。早春に他のヤナギ類よりも一足早く花を咲かせ、春の訪れを告げます。銀白色の毛で目立つ花穂がネコの尾に似ていることから「ネコヤナギ」の和名がつきました。
他のヤナギ類よりも水際に生育し、水に浸った枝先や株元から水中根を下ろします。初夏には綿毛につつまれた種子(柳絮(りゅうじょ))をふわふわと飛ばします。高さは3mほどで柔軟な枝を株元からたくさん出します。変化の大きい河川環境でいち早く成長し、増水や乾燥にも強く、陸域と水域の境界に育つ低木です。水際(エコトーン)の重要な植物ですが、近年の護岸整備により地域によっては絶滅危惧種となっています。

株元や水没した枝先から水中根を出す |
根は直根がなく、ひも状または細根で構造物に影響を与えない |
▼株元につく苔はホタルの産卵場所となる
 |
▼護岸ブロック裏に広がった根
 |
▼枝先の水中根

▼春一番に咲く花穂
 |
▼竹筒からの発根の様子。挿し木が容易。

▼枝は柔軟で強く、切れずに倒伏するため 増水時も流れを大きく阻害しない。
 |
※ 地域によっては交雑種が自生しているため、種の同定には注意を要する。
ネコヤナギ・エコ工法の手順!
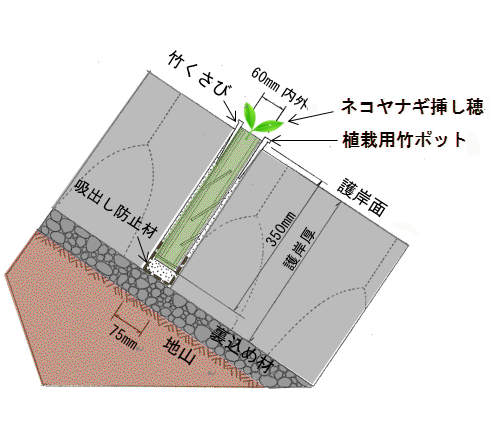
- コンクリート護岸面に水抜き穴程度(φ75)の穴をあけ、植栽用竹ポット(ネコヤナギの穂を挿し、砂を充填)を竹くさびで固定する。
- その際、根を張るスペースとなる。裏込め材まで穴を貫通させる。
- 底に吸出し防止材を設置する。
- 竹ポット周辺に砂を充填し、水が供給できるようにする。
Q:根による護岸への影響はありませんか?
A:ネコヤナギの根は細根で、コンクリート護岸への影響はありません。
Q:護岸に穴をあけても大丈夫ですか?
A:穿孔直径は護岸の水抜き孔75mmと同径で、経験的に影響がないとされています。
また、施工に際しては、吸出し防止材を設置します。
Q:ネコヤナギが大きくなりすぎて、河積を阻害し(川をせき止め)ませんか?
A:ネコヤナギは低木で枝は柔軟性があり、倒伏するので流れを大きく阻害しません。
Q:植えた後の管理はどうなりますか?
A:植栽したネコヤナギが根付いてしまえば管理は不要ですが、剪定することで更新することができます。
Q:新設護岸には適用できないのですか?
A:新設護岸にも適用できますが、工事後の河川の変化をよく見極める必要がありますので、事前にご相談ください。
Q:植えられない場所がありますか?
A:感潮区間、厚みが50cm以上のコンクリート護岸、橋梁等による陰影部、極端な水衝部などが考えられますが、施工場所、条件により異なりますので、現地調査が必要です。
※ 詳しくは弊社までお問い合わせください。
ネコヤナギ・エコ工法で生き返る水辺 3つの効果
施工位置図